子どもや保護者、同僚、来客の方々に、きちんと挨拶ができていますか?
挨拶は、日々の生活の中でつい当たり前になってしまいがちですが、保育の現場では特に
大切なコミュニケーションツールです。
この記事では、保育における挨拶のねらいや大切さについて改めて考え、子どもや保護者、
そして同僚との信頼関係を築くための具体的な挨拶のポイントをご紹介します
保育における「挨拶」のねらいと大切さ

厚生労働省の「保育所保育指針」にも記されているように、挨拶には子どもたちの成長を促す大切なねらいがあります。それが、
- 気持ちを伝え、相手を思いやる心を育む
- 安心感と心地よい人間関係を築く
詳しく説明します。
ねらい1『気持ちを伝え、相手を思いやる心を育む』
挨拶を交わすことは、自分の気持ちを言葉で伝える能力と、相手の話に耳を傾ける姿勢を
養います。
挨拶は、喜びや感謝の気持ちを伝え合う最初のステップであり、他者への関心や思いやりを
育む上で欠かせない行為です。
ねらい2『安心感と心地よい人間関係を築く』
挨拶を交わすことで、お互いの親しみが深まり、安心感が生まれます。
これは、子ども同士、保護者と先生、そして保育士同士の関係性をより良いものにし、保育園全体が心地よい生活空間になるための基礎となります。
挨拶がもたらす4つの効果

挨拶は、単なる習慣以上の価値を持ち、人間関係に様々な良い影響を与えます。挨拶を交わすことで得られる効果があります。それが以下の4点です。
- 笑顔と温かい雰囲気
- 強い信頼関係の基盤
- 会話を始めるきっかけ
- 自分と相手の自己肯定感を高める
笑顔と温かい雰囲気を生み出す
「おはようございます!」という一言が、自然と笑顔を引き出し、場の空気を和ませます。
相手に「話しやすい人だな」「親しみやすいな」と感じてもらえるため、円滑なコミュニケーションの第一歩となります。
強い信頼関係の基盤を築く
日々の挨拶は、「あなたのことをちゃんと見ていますよ」というメッセージを伝え、相手に
安心感を与えます。
これにより、互いを認め合う気持ちが芽生え、先生同士の協力体制や、子ども・保護者との
信頼関係がより強固なものになります。
会話を始めるきっかけになる
挨拶を交わすことで、自然と会話への入り口が生まれます。
特に保護者の方にとっては、挨拶を通して「この先生なら気軽に相談できそう」という
安心感が生まれ、日頃のちょっとした悩みも打ち明けやすくなるでしょう。
自分と相手の自己肯定感を高める
挨拶は、相手の存在を認め、大切に思っていることを伝える行為です。
「おはよう」と声をかけられ、笑顔で返してもらうことで、子どもたちは「自分は価値のある存在だ」と感じ、自信を育みます。
これは子どもだけでなく、挨拶を交わす双方にとって、自己肯定感を高める効果があります。
子どもに伝わる挨拶のポイント

挨拶の言葉は、「おはよう」「ありがとう」といった基本的なものから、
「大丈夫?」「よかったね」といった相手を思いやる言葉まで多岐にわたります。
その言葉をより効果的に伝えるためのポイントは以下の通りです。
- 子どもの目線に合わせて、笑顔で優しく
- 返事にはもう一度挨拶で返す
- 言葉以外のコミュニケーションも大切に
- 保護者との関わり
子どもの目線に合わせて、笑顔で優しく!
しゃがんだり前かがみになったりし、子どもの目を見て話すことがとても大切です。言葉の
やり取りがスムーズになるだけでなく、情緒的な安定にもつながります。
また表情や声のトーンにも注意が必要です。
無表情や低いトーンにならないように注意をしましょう。笑顔で優しく、穏やかな声で挨拶をするようことで、話しやすい印象や安心感を与えられやすくなります。
返事にはもう一度挨拶で返す
子どもが挨拶を返してくれたら、「おはよう!」ともう一度返してあげましょう。コミュニケーションの喜びを感じられやすくなります。
また、挨拶ができたことを褒めることも大切です。
「おっ!元気に挨拶できたね」
「すごい!かっこよく挨拶できたね」
褒められた喜びが、しだいに習慣へと変わっていきます。
心がけてみて下さいね!
言葉以外のコミュニケーションも大切に!
「さようなら」の直後にハイタッチ
手を握って「さようなら」
「さようなら」の直後にギューと抱きしめる
挨拶と動作をセットにすることで、温かい気持ちがより伝わります。
特に、言葉での挨拶が難しい0,1歳児は、上記の挨拶の仕方を取り入れることで
コミュニケーションが取りやすくなります。
1歳児から2歳、3歳と大きくなった時に、動作での挨拶から言葉での挨拶に移行して
いけるように教えてあげるようにしましょう。
保護者との関わりも大切に!
親子間での挨拶もできるようにしてあげたいですね。
登園時には「お母さんにいってらっしゃいって」
お迎え時には「お母さんにおかえりって」
保護者の方に挨拶ができるように促してあげましょう。
幼児には、みんなが集まった時に「いってらっしゃい」「おかえりなさい」の大切さを伝えてみてもいいかもしれませんね。
保育者同士こそ挨拶を大切にしよう!
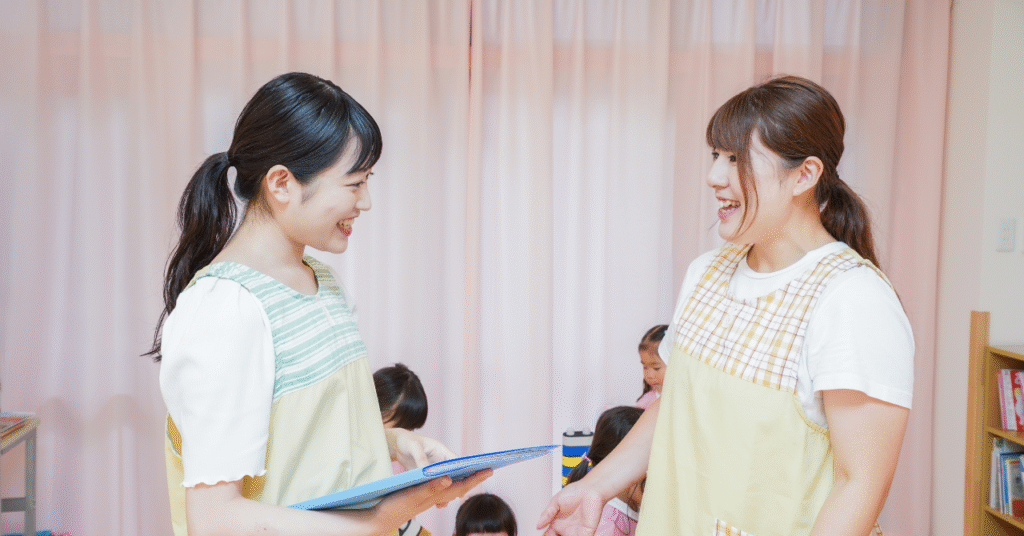
挨拶は、子どもや保護者との関係だけでなく、保育士同士にも非常に重要な効果が存在します。その効果とは以下の3点です。
- 職場の風通しを良くできる
- チームワークを高められる
- 子どもたちの見本となる
詳しく説明します。
職場の風通しを良くする
「おはようございます」
「お疲れさまでした」といった挨拶は、
話しかけやすい雰囲気、相談しやすい雰囲気、困っている時に助けを求めやすい。そんな
職場環境が生まれやすくなります。
そのため、「後輩だから」「先輩だから」という価値観は関係ありません。お互いの意識が
非常に大切です。
また、風通しの良い職場環境を目指したいのであれば、上司先輩が笑顔で優しく挨拶をしましょう。これを無視することが、職場環境を悪くしている要因かもしれません。
チームワークを高める
日頃から気持ちの良い挨拶を心がけることが、先生同士の仲を深め、自然と「協力し合おう」という協調性が生まれやすくなります。
チームワークを向上させるためにも、上司先輩後輩の立場関係なく、お互いへの敬意や感謝の気持ちを挨拶にして表現していきましょう。
子どもたちの見本となる
子どもたちは、大人の姿をよく見ています。
保育士同士が気持ちの良い挨拶を交わす姿を見せることで、子どもたち自身も
「挨拶は気持ちが良いのもだ」と学びます。
挨拶を大切にする大人の姿を見せることが、子どもたちへの最も効果的な教育の1つです。
まとめ:挨拶を日々の保育に活かそう

挨拶は、子どもや先生、保護者との間に信頼関係を築き、保育園全体をより良い場所にする
ための大切な行為です。
クラスがまとまったり、保護者からの信頼が増したり、先生同士が協力し合える関係になったりと、挨拶は様々な人間関係にプラスの効果をもたらします。
ぜひ、日々の保育の中で挨拶を大切にし、子どもたちの豊かな心と、先生自身のやりがいを
育んでいきましょう。
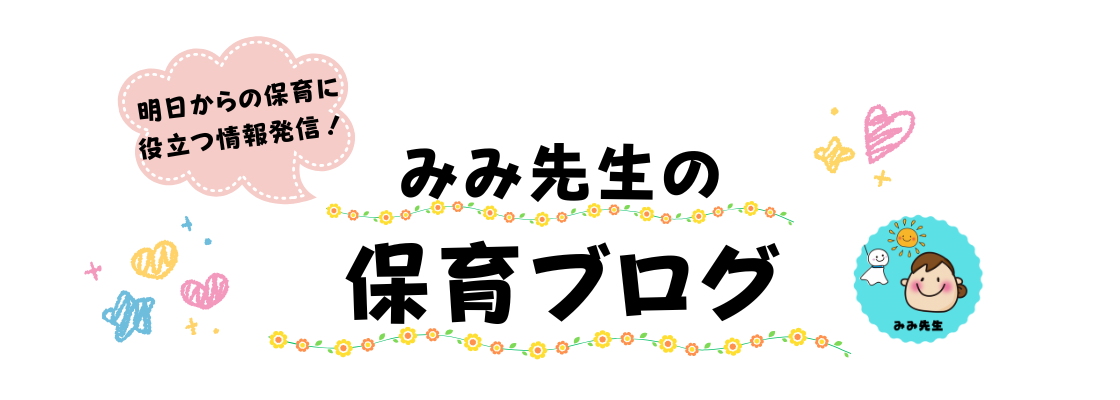
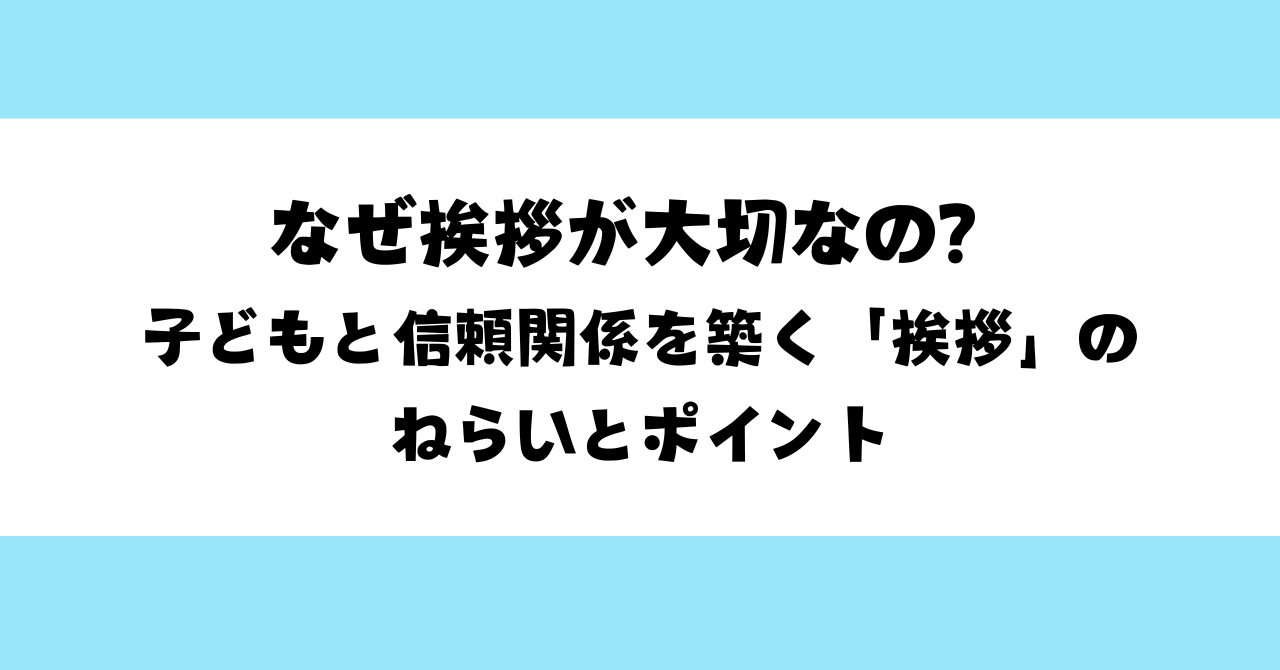
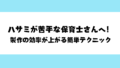
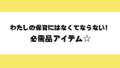
コメント