今回は、『ADHA』について深掘りしていきます。
「少しもじっとしていられない、どう対応したらいいの?」
「友だちとのトラブルが絶えなくて...」
そう感じている先生は少なくないのではないかと思います。わたし自身も、個別の援助が必要な子
と向き合い、その子への関わり方を試行錯誤してきました。
この記事では、わたしの実体験を含めながら、具体的な関わり方やヒントをお伝えします。
ADHDへの理解を深め、その子に合った保育を見つけるヒントになってくれたら嬉しいです。
ADHDとは?

『ADHD』とは、
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
の頭文字をとってもので、
日本語では、『注意欠如・多動症』または、『注意欠如・多動性障害』と翻訳されます。
年齢や発達に不釣り合いな不注意さ、衝動性、多動性を特徴とする発達障がいの1つです。
必ずしも、3つの特性すべてが現れるのではなく、
不注意だけが目立つ子
多動性や衝動性が目立つ子
というように特性はさまざまです。
ADHDの診断は、ご存じだと思いますが、専門医が行うものです。
わたしたち保育士は日々のかかわりの中で、その子の特性を正しく理解し、適切なかかわり方を
するのがとても重要です。
ADHDの特性は、その子の個性として素晴らしい一面を持ち合わせていますが、
同時に、日常生活や集団生活に困難が生じる原因となることがあります。
度を越えて、生活に支障をきたしたり、集団に適応できなかったりし、理解されにくく、
誤解されやすい...
だからこそ、身近な存在である保育士が、その子の特性を正しく理解し、受け止める必要が
あります。
特性とは?

特性についてお話します。
不注意の特性は、以下のような行動となって現れることが多いです。
不注意がある子の特性
気が散りやすく集中力が続きにくい、また忘れっぽいといった姿として見られます。
・長い時間、1つのことに集中できない
・気が散りやすい
・集中しすぎて、切り替えが難しい
・途中でやめることが難しい
・話しかられても気づかない
・話を聞いていないように見える
・うわの空でボーっとしているように見える
・忘れ物、失くしものが多い
・言われたこと、約束を忘れる
・同じミスを繰り返す
・整理整頓、片づけが苦手
具体例
以下のような行動が見られます。
- 片づけをしようと始めても、そこにある絵本に読みふけってしまう。
- 虫が飛んできた、と反応してその場を離れてしまう。
- 面と向かって話していても、聞いていないように見えてしまう。
多動性がある子の特性
じっとしているのが苦手で、常に動き回り、落ち着きがない。しゃべりだすと止まらないという
姿も見られます。
・立ち歩いてします
・座っていられない
・座っても手足がそわそわ動く
・常に体のどこかが動いている
・気になるところへ行ってしまう
・高いところに登ったり、跳び下りたりする
・話しだすと止まらない
・順番を抜かしてしまう
・話の内容がころころ変わる
具体例
以下のような行動が見られます。
- 話を聞いているときに、座っていられず、立ち歩いてしまう
- イスをガタガタさせるのが止まらない
- 話しだすと止まらなくなり、声も大きい
衝動性がある子の特性
感情のコントロールが難しく、考える前に行動してしまいます。
何かをする前に、立ち止まって考えるのが苦手です。
・待つこと、我慢が苦手
・質問が終わらないうちに答える
・指名されていないのに発言する
・思い込みでしゃべってしまう
・思い通りにいかないと、暴れたり、
乱暴したりする
・思ったらすぐに行動してしまう
・横入りしたり、順番が待てなかったりする
・気になったものは触らずにはいられない
・あそびや生活のルールが守れない
・人のものを勝手に取ったり使ったりする。
具体例
以下のような行動が見られます。
- 順番が待てずに横入りしてしまう
- ルールを守れずにどんどん先に進めてしまう
- 急に道に飛び出したり、危険な場所に入ったりしてしまう
- 高いところから跳び下りてしまう
- カッとなった瞬間、手が出てしまう
- 癇癪を自分では抑えられない
そのため友だちからは、「乱暴」「怖い」「すぐキレる」「怒りっぽい」などと捉えられ、友だち関係がうまく築けないことも多くあります
関わり方のポイント

環境を整える
例えば、
『朝のお支度を自分でして欲しい』
『片づけをしてくれない』
何をするべきか分かりやすいよう、絵や写真と文字などと活用し、視覚的に示す工夫が必要です。
また、
「タオルはこの箱だよ」
「連絡帳は青いカゴだよ」
と実況中継をしながら片づけ方を見せていくのもいいでしょう。
『すぐに気が散ってしまう』
『持続できるようになってほしい』
こういった場合には、
活動に必要ないものは片づける
魅力的なものは、視界に入らないように移動させる
などといった、見えるもの、聞こえる音など、周囲の刺激を減らし、集中しやすい環境作りを
心がけましょう。
また、以下のような方法も効果的です。
「これから2つのお話をするよ。まず1つ目は・・・」→「お話ちゃんと聞けたね。えらいね」→「お外行こうか」
話す時に気が散らないような環境の工夫も合わせると非常にいいでしょう。
話をわかりやすく伝える
ADHDのある子は1つのことに集中し続けることが難しいため、長い説明や抽象的な言葉は
避けるようにします。
例えば、
「頑張って」→「あと1回だよ。頑張って」
「優しくしてね」→「よしよししてあげてね」
「ちゃんとして」→「お片づけをしたら、次の遊びをしようね」
と具体的に伝えるようにします。
また、一度に多くのことを指示せず、言葉を短く区切り、確認しながら話すように心がけます。
絵や写真、ジェスチャーなどの視覚的な要素も加えると、さらに分かりやすくなります。
また、その子と話をするときは、向き合って手を握ったり、腕を触ったりし、「○○くん聞いて」「お話するね」と声をかけて下さい。
「今からお話をする」が伝わってから話し始めるようにしましょう。
スモールステップで
ADHDのある子の中には、『ワーキングメモリ』が上手く働かないケースがあります。
『ワーキングメモリ』とは、脳のメモ帳と言われており、例えば、
「はさみとのりを持ってきてください」の指示で、その3つの物を一時的に記憶して持ってくる
ことを言います。
午睡の起床時だと、
起きたら→トイレに行く→手を洗う→布団を○○に片づける→お茶を飲む→椅子に座る
と行動を1つずつ区切ると、わかりやすく簡単になります。
また、1つずつ終わるたびに「できたね。えらいね。」「OK!できたね。」と褒めることで
達成感が持てるようになります。
活動では、ちょっとの頑張りで達成できることを目標にしましょう。
できたら褒めるが大切になるように!!
できたことを褒める
ちょっとしたことでも、すぐに褒めるようにしましょう。
頭をなでたり、両手で大きな丸を作ったり、身振りを交えて褒めたりしてあげて下さい。
「まるー!」「ピンポーン!」でもGoodです!
しかしながら、褒めることが大事だと分かっていても困った行動が目立ってしまう為、その子の
マイナス面ばかりが見えてしまいます。
だからこそ改めて、その子の良いところをゆっくりと思い出してみて下さい。書き出してみるのも
いいでしょう。
また、『意図的に褒める』そういった瞬間を、自ら作ってください。
誰かに届けてもらう、持ってきてもらう答えてもらう、おだててみる など
本当にちょっとしたことでOKです。
褒めるという行為が、先生自身の心を軽くし、気持ちにも余裕が生まれてきます。
その子のプラス面や成長した面が見えてくるようになります。
これは、わたしの実体験です。ぜひ、参考にされてみて下さい。
くどくど叱らない
まずは振り返ってみて下さい。その子に注意をしている時のこと...
注意したことを分かってくれたの?
ちゃんと聞いているの?
そんな場面も少なくないと思います。
注意をする上でのポイントは、いちばん大切なことを端的に伝えることです。
遠くから大声で伝えてはNGです。
子どもの顔を見ながら、穏やかに、落ち着いた声で話しかけるよう心がけましょう。
イライラしたり声を荒げたりしてはいけません。
人格を否定するような言葉もNGです。
「だめ」
「やめて」
「何回言ったらわかるの」
「いい加減にしなさい」
もNGです。
「走らないで」→「歩こうね」
「投げない」→「下に置こうね」
と肯定的な言葉で伝えて下さい。
失敗やミスは責めるのではなく、一緒に解決策を考える姿勢で接しましょう。
そして、注意することを厳選してください。
わたしの場合は、
他者に痛いことをわざとした時、
危ないことを繰り返しした時
にしました。
それ以外は、他者に迷惑がかからなければ、怪我に繋がらなければ、OKとしました。
許容範囲を決めておくと、ストレスが減ります。
その子のマイナス面が減り、プラス面が良く見えるようになります。
注意が減り、褒めることが増えます。
これも実体験です!!
友だちとのトラブルには...

友だちが使っているものを勝手に取ったり、
並んでいる列に横入りしたり、
カッとなって手が出てしまったり、
とにかくトラブルが絶えない...そんな悩みを抱えた先生もいますよね。
「~したい」という思いが先行してしまい、感情を抑えることが苦手なんです。
その結果、周囲から「いじわる」「わがまま」捉えられてしまいます。
その場のルールや感情のコントロール人とのかかわりで必要なことを教えていくそれもわたしたちの役割です。
伝える時に大切にしたいこと
気持ちを受け止めてから
「取っちゃダメでしょ!」「叩いたらダメ!」と頭ごなしに叱ってはいけません。
まずは、静かな場所に移動し、少し落ち着いたところで、
「あのおもちゃが欲しかったね」
と、その子の思いを受け止め、共感しましょう。
それにより、大人の話しが少しずつ入っていくようになります。
怒った表情はNG、穏やかな表情で話しかけるようにしてください。
気持ちを受け止めたうえで、
「でも、勝手に取ってはいけないよ」→「使いたいときは貸しだよ」→「お友だちがいいよって言ったら取るんだよ」
の順番に教えていきます。
「貸してって言うときは、手を横につけるんだよ」
と教えてもいいでしょう。
気をつけることは、相手の視点で言い聞かせようとしないことです。
相手の視点というのは、すぐに理解できるものではありません。
ゆっくりでも必ず身についていくので、根気よくくり返し伝えていってください
客観的に教えてあげて
「順番」「並ぶ」とは何かを教えてあげることも大切です。
「1,2、3人並んでいるね。○○ちゃんは4番目だよ。」
「○○ちゃんは△くんの後ろだよ。」
という声かけ方を心がけてみましょう。
割り込んでしまった場合は、本人の気持ちを受け止めた上で、
「誰が滑り台していた?」
「並んでいたのは何人?」
などと、その場の状況を振り返りながら確認しましょう。
衝動的に動いてしまう前に声をかけることも大切です。
「並ぼうね」「順番ね」と気づかせてあげて下さい。わざとではないので、状況が分かれば、
待つこともできます。
待てた、並べたことをしっかりと褒めてあげて下さい。失敗しながらも、待てた経験をくり返すうちに少しずつ身についていきます。
あったか言葉
まずは先生自身が肯定的な「あったか言葉」を日常的にたくさん使うよう意識しましょう。
「○○ちゃんの絵じょうずだね!!」
「△くんが~してくれて嬉しいね。
「~してくれたの、ありがとう」
先生自身が、肯定的な言葉や相手温かくなる言葉を、自然と教えられるようになります。
相手を傷つける言葉を言ってしまった場合は、「自分がされたらどう思う?」と、自分の気持ちに置き換えてから相手も同じ気持ちなんだよということを説明していくといいでしょう。
最後に

ADHDのある子への関わり方を理解することは出来ましたか?
よく見てみると、その子だけの特別な関わり方ではなく、当たり前のかかわり方が多い印象
だったと思います。
そうは言っても衝動的に動かれてしまったり、他の子と違うことをされてしまったりすると、
混乱してしまいますよね。
だからこそ、ADHDのある子への関わり方を見返して、
「そうだそうだ、そうだった!」
「なんだ、いつもやっていることだ!」
そう感じてもらえるだけでも、気持ちが少し軽くなると思います。
1人で抱え込まずに、誰かを頼ってください。
まずは、身近な存在、先輩でも、主任でも、園長でもOKです。
甘えていいんです。誰かと一緒に解決していきましょう。
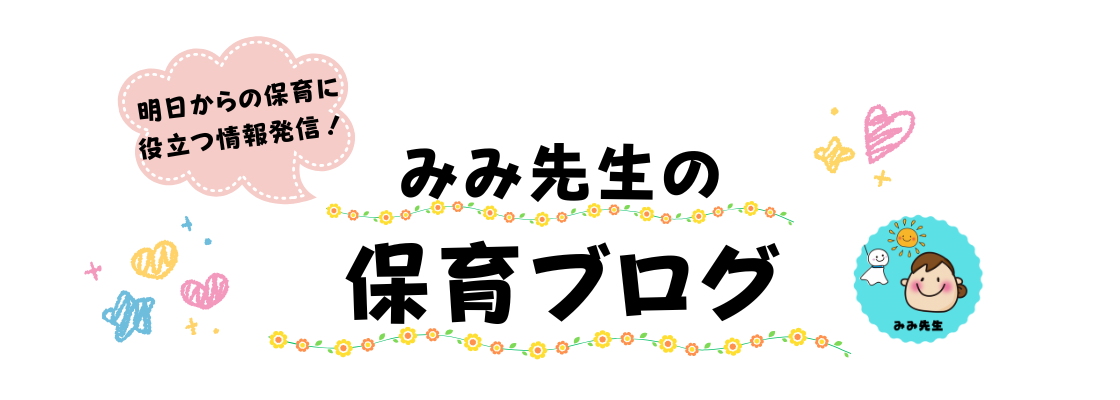
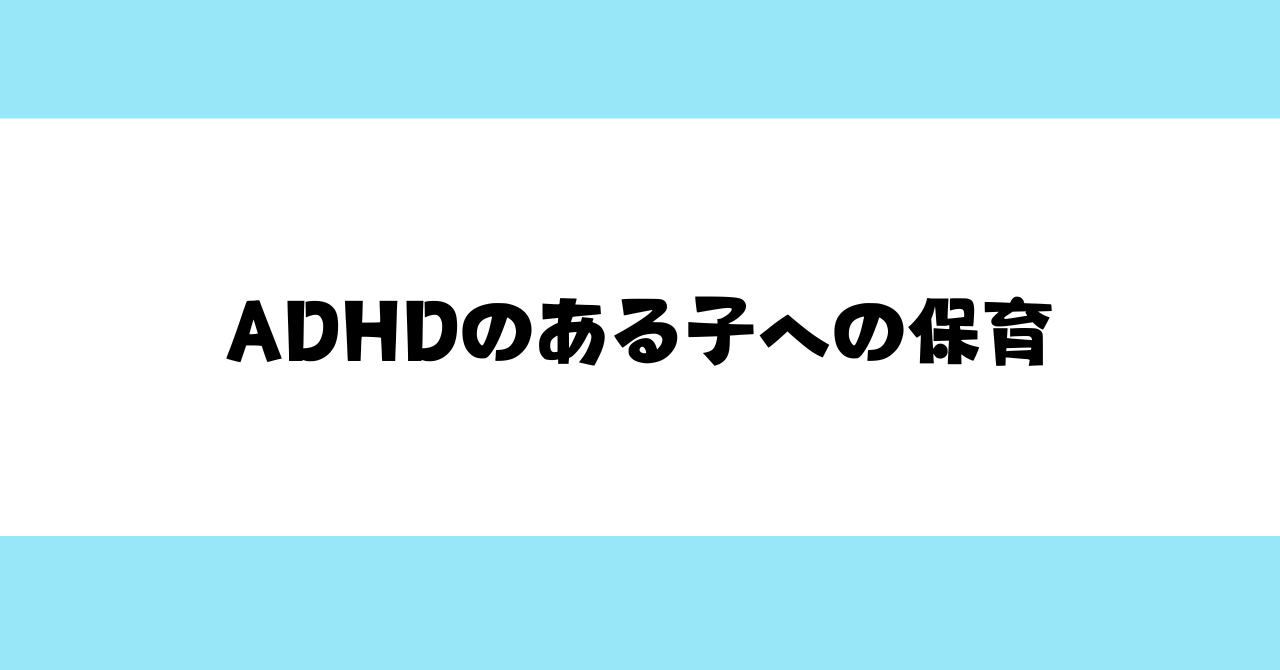
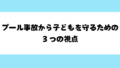
コメント